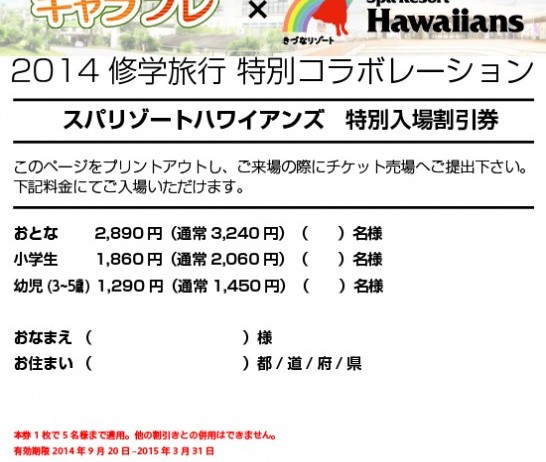文章:春日康徳
いまさらながら、
「後悔」
という文字は「後から悔いる」と書く。
思えばなぜ、あのとき掃除をしようと考えたのか。役員たちには、きもちのいい場所で仕事をしてほしい。それだけだった。なのに……余計な気をまわさなければ、あるいは……。
生徒会室の給湯場で、茅野瑞希(かやの・みずき)は激しい後悔の念にさいなまれていた。頼りなげな眉をハの字にした茅野は、大きくため息をつく。頭のなかは、さきほどからなんどもおなじ後悔の言葉が渦巻くだけだ。
茅野の足もとには、粉砕された湯飲みが無残にも散らばっている。

ただの湯飲みでは、ない。
日本茶の愛好家である生徒会長・五十嵐飛鳥がたいせつにする、焼き物の湯飲みである。
(謝って、はたして許されるものか?)
茅野は思考実験した。いつもミスをするたびに飛鳥にどやされてきた茅野である。素直に湯飲みを割ってしまったことを謝れば、いっときは茅野に雷を落とすだろうが、嵐さえすぎされば……。
しかし、同時に茅野はその湯飲みを大事にする飛鳥の姿を思い起こしていた。彼女はその湯飲みでしか、日本茶を飲まない。相当なこだわりがあるらしかった。
まして、何度もミスを連発している茅野だ。先日も大事な書類の束を床にばらまいて、大目玉をくらったばかりだった。もはや飛鳥は、部下として茅野をまったく信用していないだろう。
そんな現状なのに、会長の大切な湯飲みまで割ってしまった……。もはや信頼回復など夢のまた夢だろう。
心苦しかった。飛鳥のために、なにかしたい。この人に認められたい。そう想って一生懸命にやることなすこと、すべて裏目に出てしまう。
不甲斐ない自分にますます嫌気を感じながらも、茅野はあるひとつの結論に達していた。
(なんとかごまかせないものか……)
顎に手をあてて考えを巡らせていると、不意に生徒会室の引き戸が音をたてて開かれた。びくっと警戒して茅野が振りかえると、
「こんにちは」
と笑顔であいさつしてくる女子生徒の姿があった。彼女はつい先日、翔愛学園に転入してきた生徒である。生徒会の書類を廊下にばらまき、飛鳥会長に怒られた際、偶然居合わせた彼女は茅野に味方してくれた。
『こんなたくさんの書類をひとりで運べるはずがありません!』
と。
結果、その正義と義務感を飛鳥会長に買われた転入生は、生徒会特別役員として運営に関わっていくことになったのだった。
特別役員——『メイド』として……。
「茅野さん、どうされたんですか? 顔色が悪いですよ? また、なにか失敗を?」
心配げに訊ねてくる彼女に二の句を継げず、「ま、また……って……」というしかない茅野は、「ううっ、どうせ僕は失敗ばかりで、みなさんの足をひっぱってますからね……」といじけてみせるしかなかった。
「ご、ごめんなさい。そういう意味では……」
いいながら、彼女が茅野の足もとで起きている異変に気づいて、視線を落とす。
「ああ!」
思わず声をあげ、指さして、
「まさか、茅野さん!」
茅野は認めるしかなかった。瞑目し、「僕がやってしまいました」と応える。
「会長の……湯飲み……」
茫然とする彼女にすがる思いで、茅野は「どうしたらいいでしょう?」と訊ねた。
「おなじものを買って弁償……ですかね?」
茅野は首を振った。
「おそらくこの湯飲みはひとつで数万円はします……」
「え、そんなに!?」
あらためて彼女は割れた湯飲みの破片に眼を落とす。
「生徒会ってお金あるんですね……」
「理事長先生にもらったと聞いています。なんでも、理事長先生もおなじ湯飲みをお持ちだそうで……」
「でしたら!」
思わず浮かんだアイディアに手を叩いた彼女は、「理事長先生にお願いして譲ってもらったらいかがでしょう?」
と提案する。
「……ゆ、譲ってくれるでしょうか?」
茅野が訊ねると、彼女は苦り切った表情で、「う~ん。さすがに数万円もする物を、簡単には譲ってくれないですよね……」と答えを絞りだす。
なんとかならぬものか。理事長の湯飲みと割れた湯飲みを差し替えれば、すべては丸く収まる。たしかに飛鳥会長の湯飲みを割ってしまったことを黙っているのは気が引けることではある。しかしそれは、怒られるのがいやだとか、そんなつまらぬことではなく、なにより湯飲みを大事にしていた会長を悲しませないためであった。
「理事長に……話をしてみます」
悲愴な決意で茅野はいった。
「譲ってもらえないか、お願いしてみます」
「茅野さん……」
そんな茅野に悲哀を感じたのか、彼女は「いっしょに行きましょうか?」と気遣ってくれる。
「えっ……いっしょにお願いしてくださるんですか?」
「だって……放っておけないじゃないですか」
彼女はにっこりと笑って応えた。
湯飲みを割ってからというもの、まるで生き地獄にいるようだった茅野にとって、彼女の笑顔は一条の希望の光だった。
「では……ぜひおねがいします!」
茅野は勢いよく彼女に頭をさげた。
「そんな、やめてください……」
困ったように手を振る彼女に、茅野は、
「『メイド』さん……」
と呼びかける。
「え、『メイド』さん?」
「あ、いえ、失礼しました。特別役員『メイド』さん」
「もう……『メイド』でいいですよ」
諦めたように彼女はいう。
「あ、ところで……」
ふと足もとで散らばる湯飲みの破片に気がついた茅野は、「割れた湯呑は、どうしましょうか?」と問うた。
「そうだなぁ……捨ててしまっていいんじゃないでしょうか。証拠隠滅ということで……」
彼女は最後の言葉をささやくようにいった。茅野は手早く割れた湯飲みをちりとりで回収し、『割れ物』と厚手の紙袋に捨てて、それをゴミ捨て場に持っていった。
そして、2人は理事長室へ歩を向けたのだった。
「実は、理事長先生から生徒会長がいただいた湯呑を、うっかり割ってしまったんです。せっかくの高価な品なのに……」
茅野が申し訳をひらいていた。おそろしさのあまり、彼は目の前の理事長と目を合わせられずにいる。
「なんと、あの湯呑を!」
眼鏡越しに理事長は目を瞠った。普段は穏やかな眉間に厳しいしわが刻まれ、理事長室はいっしゅん、緊迫した空気に包まれた。
「う~む、そうか……」
感情を荒げてもしかたがない。大人な理事長はただただ無念というように唸って、「あれはいい湯呑じゃった……」とこぼした。
「ほ、本当に申し訳ありません!」
茅野が頭を下げるのと同時に、となりにいた特別役員も頭を下げる。
「まあ、失敗は誰にでもあることじゃ」
目の前の生徒2人に頭を下げられ、どこか居心地の悪さを感じているらしい理事長は、努めて明るくいった。
「次からは注意して扱うことじゃな」
「は、はいっ!」
「まあ、次はないじゃろうが……」
そう言われてしまうと、『理事長の湯飲みを譲ってください』とはいいにくい。茅野はとなりにいる彼女へ目で助けを求めたが、ちいさく首を振るだけだった。
「……ところで?」
咳きこんだ理事長が、眼鏡を押しあげていう。
「陶磁器には色々種類があるが、あの湯呑が何かわかるかね?」
「えっ!? 湯呑の種類……ですか?」
茅野と彼女はまったく予想外の質問をぶつけられ、当惑する。
「ヒントは、京都の名産品なんじゃがのう」
「京都って言えば……伊万里焼…ですか?」
なんとか言葉を継いで、雰囲気をやわらげようとした茅野だったが、
「残念ながら不正解じゃ!」
というにべもない理事長の応えに顔をうつむけてしまう。
「あれはのう、京都の清水焼じゃよ」
彼女が、はやく理事長にお願いしたらどうですか、と肘で茅野をせっつく。はやくも諦めモードになっている茅野は、先の悲愴な決意はなんのその、戦意を喪失していた。
「はっはっはっ。わかっておるよ!」

突然、哄笑をはっする理事長に茫然としながら、茅野と彼女は「え?」とその真意を問うた。
「君たちの心が読めないで、理事長など務まらんからな」
「では……」
いいにくかったことを、理事長はどうやら察してくれているらしい。一縷の希望を見出したかのように、茅野が身を乗りだす。
「その目は、清水焼について詳しく知りたいという目じゃな?」
「え……?」
まったく見当違いの理事長だった。しかし、ここまで身を乗り出しておいて、そうではありませんとはいえない。
「はい、ぜひ教えてください!」
もはややけくそ気味に茅野はいった。
「はっはっはっ! 本当にキミは勉強熱心じゃの。では、教えてしんぜよう。京焼・清水焼とは、京都で焼かれた陶磁器の総称なんじゃよ。本格的に作られるようになったのは、安土桃山時代の末からでの。江戸時代になると京焼の祖というわれる野々村仁清によって、かつてない、繊細で華麗な色彩の陶器が作られるようになったんじゃ。
その後も、数々の名工を輩出したんじゃ。まあ、そういった伝統を受け継いだ清水焼の特徴はの、大量生産、機械化に頼らずに、すべて手作りだということが特徴なんじゃよ。うーむ。素晴らしいのう……どうだね?」
「は、はい。大変素晴らしいものだということはよくわかりました!」
そんな追従の茅野にしびれを切らした彼女は、
「その清水焼なんですが!」
と思い切って話を切り出した。
「ん? なんだね?」
「実は折り入ってご相談が……」
「ほうほう。言ってみなさい」
とんとん拍子で話が進んでいく。うまくいってくれと茅野は祈るように話の成り行きを見守った。
「あの、理事長先生がお持ちの湯呑を、譲ってもらえないでしょうか……?」
「なに!? わしの湯呑を譲って欲しいじゃと!?」
「は、はい……」
理事長は顎に手をあてて黙考にはいった。沈黙はつづく。やはり無理なのか……諦めかけたそのとき、
「うむ…まあ、他ならぬ君の頼みじゃ。譲ってやらんでもないが……」
と思案しながら理事長がいった。
「えっ、本当ですか!?」
思わず茅野が声をあげる。
「じゃが!」
そんな茅野を制止するかのように、理事長が条件をつける。
「この湯呑は、わしにとっても大切なものじゃ。タダというわけにはいかん。おなじくらい価値のあるものと交換する、というのが条件じゃ」
等価交換――高価な湯飲みと交換するようなものを自分はなにももちあわせていない。それは彼女とておなじことだろう。2人はまたしても目を合わせ、当惑し、無念のため息をついた。
「すみません、わたしたち、その湯飲みと交換できそうな高価なものはありそうにないです……」
「なにも高価なものを要求しようというのではないよ!」理事長はおもしろがるようにいった。「割れた湯呑と交換しようかのう?」
「え!? 割れた湯呑ですか?」
「いかにも」
謎かけのような理事長の要求に、茅野と彼女はふたたび面をあわせる。刹那、茅野は理事長室へ来る前に、割れた湯飲みをゴミ捨て場に置いてきたことを思い出し、
「いけない!」
と声をあげた。
すぐに彼女もそのことに気づいたらしく、目を見開いた。
「……どうかしたかね?」
「あの、いますぐ持ってきますので、少々お待ちください!」
茅野は走った。一心不乱に廊下を駆け抜けた。途中、体育の柏木教諭が「コラ! 廊下を走るな!」と呼び止めたが、茅野は無視してゴミ捨て場に急行した。
飛鳥会長を悲しませたくない。つまらぬミスを連発し、いつもいつも彼女を怒らせている自分。そんな不甲斐ない自分が、さらには会長の大事にしている湯飲みまで割ってしまった。
彼女の期待を裏切りたくない。失望させたくない。そんなことを一心に願って、茅野は走りに走った。
校舎裏のゴミ捨て場に着くと、そこには最前まであったはずのゴミの山は消えていた。遠くでトラックのエンジン音が聞こえる。どうやらすれ違いだったらしい。
一気に放心状態になった茅野は、その場に膝をついた。あとから追いついてきた彼女が、「茅野さん、どうでした!?」と問うてくる。
静かに首を横に振った茅野は、「会長に謝ります」とちいさい声で洩らした。
「もともと僕の不注意だったんです……」
沈痛な茅野とは反対に、無邪気な女の子の笑い声が、ふいに空からふってきた。
空耳ではない。茅野と彼女は目をあわせ、
「……聞こえていますよね?」
と確認し合った。
刹那、まばゆいばかりの光が炸裂して、2人の眼前に白いワンピースを着たブロンド髪の少女があらわれた。
「ミ、ミカちゃん!!」

彼女が呼びかける。
「天使……!?」
これがみなのいう天使か。茅野は茫然としながら、少女がにっこりとほほえみかける野確認した。
ふたたび光の炸裂が起こり、気がついたときにはミカちゃんは消えていた。
――その代わりに。
2人の眼前には、厚手の紙袋が置いてあった。見覚えがある。まさかとは思いつつ、茅野は紙袋の中身をあらためた。
「割れた湯呑が!」
振り返り、茅野は特別役員に報告する。
「どうしてここに? ゴミ収集車が持っていったはずでしょう……?」彼女はそういってから、「もしかしてミカちゃんが……?」
と言葉を継いだ。
取り戻せぬはずのものを、ミカちゃんが奇跡を起こしてくれた。そうと合点がいくまでには、数秒を要した。
「理事長先生! 割れた湯呑を持ってきました!」
茅野は特別役員とともにふたたび理事長室を訪れていた。穏やかな笑顔で出迎えてくれた理事長は、
「よしよし、では交換しようではないか」
と大切なもうひとつの湯飲みを取り出した。
あらためて受け取ろうと手を伸ばした茅野は、しかし、いったん手を引っこめた。そんな挙動の茅野を、彼女が横目で不審がる。
「どうしたんですか、茅野さん」
「いえ……」
「なにか釈然としないという顔をしているな」
茅野の心の裡を察したらしい理事長がいう。
「え、あ、あの……」
見透かされたようで、動揺する茅野をよそに、理事長はさらに「わしがこんな割れた湯呑と交換しようとしているのが不思議かね?」
と見事に言い当ててくる。
「は、はい……正直、理事長先生の真意がよくわかりません……」
普通に考えれば、割れた湯飲みなど、ただのごみでしかない。そんなものをほしがるのは、理事長の気遣いからなのか、あるいは……。
「まあ、君にもいずれわかる時がくるじゃろうて」
そう言葉をにごした理事長は、あたらしい湯飲みを茅野に進めてきた。
いまはとにかく、湯飲みが割れたことに気づかれる前に、この湯飲みを置いておかなければならない。それ以上の疑問にすべて蓋をした茅野は、湯飲みを受け取ると、理事長に礼をいって去っていった。
「なにはともあれ、湯飲みを譲ってもらえてよかったですね!」
ほっと胸をなで下ろす茅野に、彼女が声をかける。
「ええ、ひとまずは……」
窮地を綱渡りで乗り越えた心持ちの茅野は、生徒会室の引き戸を引いて、なかにはいっていった。
「おはよう、茅野!」
室内からは、飛鳥会長の朗らかな声があがった。
茅野と彼女は、茫然とし、すぐに持っていた湯飲みを背後に隠した。
「あら、『メイド』もいたの?」
「特別役員です!」
茅野が彼女をかばうようにいう。
「どうせ暇なんでしょ? お茶でも煎れてくれないかしら?」
「は、はい……」
茅野と彼女はひそかに目を合わせた。どうやらまだバレていないらしい。大切な湯飲みが割れていることを知ったならば、会長はたちまち赫怒しているはずだ。
茅野は彼女に湯飲みを渡した。彼女はお茶をいれるためにさがっていく。
飛鳥会長は書類に目を通し、集中していた。茅野は手持ちぶさたのまま、おとなしく生徒会室の片隅の机にこしかける。
まもなく、彼女の淹れたお茶がやってきた。運ばれてきた湯飲みで飛鳥会長は一口茶をすする。
そして、
「茅野!」
と急に呼ばわった。
「は、はい!!」
条件反射的に、茅野は踵をあわせて立ちあがった。
「私のお気に入りの湯呑。清水焼のやつなんだけど……知らないかしら?」

「清水焼ですか!? それでしたらいま飲まれているのが……」
「そう……よねぇ?」
飛鳥は湯飲みを眺めながら、不審の色を浮かべている。
「ねえ! あなたは知らない?」
茅野の答えに不満だったのか、飛鳥会長は彼女にも聞きなおす。
「え……?」
とっさに誤魔化す言葉が見つからなかったのか、彼女はしどろもどろになっていった。
「私の湯呑を知らないかと聞いているの!」
しびれをきらして、飛鳥会長が語調を強める。
「……会長の湯呑なら、いまつかっていらっしゃるのがそうなのでは……」
「それがねぇ。これ、私のじゃないのよ。清水焼は、どれも職人さんが一つ一つ手作業で作っているから、微妙な違いがあるんだけど……」
茅野は胃のなかがひっくり返るかと思った。看破されたことに激しく動揺し、恐怖で膝が震え出す。
「………おかしいわよねぇ? 私の湯呑は、いったいどこへいってしまったのかしらね~ぇ?」
絶対にバレてる。なのにすっとぼけている風の飛鳥会長の冷静さが、逆に空怖ろしい。なにも言葉を紡げずにいると、
「か、勘違いじゃないですか?」
と果敢に彼女がいった。
「湯呑が変わっているはずないですよ。誰がそんなことするんですか」
「そう……。とぼけるつもりなのね?」
「と、とぼけてなんか……」
「嘘をついてもダメよ!」
飛鳥会長がバンと机を叩いた。
「茅野の目を見れば、わかるわ!! この湯呑みは、ゑびちゃんのでしょう?」

ゑびちゃんとは理事長先生のことだ。縁戚関係の飛鳥は、先生をそう呼んでいる。
「す、すみません……」
茅野と彼女は、これ以上は言い訳ができぬと観念し、とにかく頭を下げた。
「まったく……」飛鳥は腰に手を当て、大きく嘆息した。「あなたには、本当にがっかりだわ! どこか見所がある……なんて考えた私がバカだったわ!!」
茅野ではなく、彼女に向けられたその言葉に、茅野は罪悪間にさいなまれた。
もともとは自分のミスだ。そのミスをいっしょになって庇おうとしてくれた彼女の信用をも、自分は傷つけてしまった。取り返しのつかぬことをしてしまったという後悔が、ふたたび胸を締めあげていく。
そんな重苦しい空気が漂うなか、どこからともなく、女の子の笑い声がした。
「ちょっと!何笑ってるのよ!?」
飛鳥が鋭い視線を茅野に向ける。
「いえ、僕では……」
刹那、ふたたび茅野と彼女の前に、天使・ミカちゃんがあらわれた。
「ミカちゃんが……」
「ミカちゃん?」
飛鳥も振り返ると、ミカちゃんは無邪気に微笑んだ。そしてまた、すうっといなくなってしまう。
「ふぅ………」
飛鳥が気分を入れ替えるように息を吐いた。
「そうね……。まあ、悪気があってやったことじゃないものね」
「嘘をついたわたしが間違ってました」
茅野の代わりに、彼女が前に進み出ていう。
「ええ。だから、今度からは本当のことを打ち明けてちょうだいね」
「は、はいっ!」
どうやらミカちゃんのおかげで、会長は機嫌を直してくれたようだった。
「いいこと。あの湯呑はとっても大切なものなの。割れた湯呑を取り返してきてくれるかしら?」
「え? 割れた湯飲みを?」
どうしてそんなものを欲しがるのか。不審に思った茅野が確認すると、
「いいから取り返してきなさい!!」
と茅野と彼女をまるで追い払うかのようにいった。せっかく譲ってもらったのに、理事長になんといっていいやらもまったく見当がつかぬまま、2人は生徒会室を去っていった。
思えば、理事長も割れた湯飲みを欲しがっていた。あのときは『いずれわかるじゃろうて』ともいっていた。
まずは飛鳥会長の気持ちを損ねないことが肝要だ。茅野は彼女とともに廊下を急いだ。
「おや。また、君たちかい? 今度はどうしたのかね?」」
おもしろがるように、理事長はいった。どうやらすべての事情を察しているらしい訳知り顔をしている。
「あの……この湯呑、お返しします」
彼女がもらいうけた湯飲みをおずおずと差しだした。
「お返ししますので、どうか代わりに割れた湯呑を返していただきたいんです」
申し訳なさそうに告白すると、理事長は「はっはっは」とのけぞって哄笑をもらす。
「せっかく交換したというのに、君たちもなかなか忙しいのう?」
「すみません……。生徒会長が元の湯呑を持ってきなさいって……」
茅野が補足する。
「わかった……。では、これを持っていきなさい」

そういって理事長が差しだしたのは、割れていない、もうひとつの湯飲みだった。どうやら柄は生徒会長のものとおなじようだが……。
そんなはずはない。茅野はいま自分の頭に浮かんだ考えを打ち消した。理事長と交換したのは、割れた湯飲みだったはずで……。
「割れた湯呑を修理したんじゃよ」
戸惑う茅野たちに理事長が答える。そういわれてみると、たしかに湯飲みには修復の跡が確認できた。
「こうして見ると、壊れた跡も味があると思わんかね? 同じ傷のついた湯呑はどこにもないんじゃ。世界に一つの品というわけじゃのう」
「では……この湯飲みを持っていきます」
「うむ、よかろう」
「失礼します!」
理事長からふたたびもらい受けた湯飲みを飛鳥会長に差しだすと、戻ってきた湯飲みを吟味した上で、
「なるほど。綺麗に修理してあるわね……」
とまずまずの反応だった。
茅野と彼女はほっと胸をなで下ろした。
「……どうして私が、元の湯呑を取り戻してこいと言ったか、わかる?」
「いえ……」
茅野と彼女が同時に首を振る。
「茶道ではね。茶器が壊れても買い替えたりしないで、出来る限り修理して使うものなの。ものに感謝して大切にする心が重要なの。もちろん、壊さないように丁寧に扱うことが一番だけど。割れた跡……。今度は、そのひびの形を楽しむのよ」
ものを大切にする心——理事長と会長がそれぞれ割れた湯飲みでも所望したのは、そういうことだったのか。ようやく合点がいった茅野は、心のなかで膝を打っていた。
「で、結局湯飲みを割ったのは茅野なわけね?」
「あ、はい! すみません!」
「まったく……」
飛鳥は呆れたように鼻で笑った。彼女に目を向け、
「あなたもあいかわらずの物好きね。茅野のミスを庇うなんて……」
「だって……困ってる人、見過ごせないじゃないですか」
彼女の答えにさらに笑みを大きくした飛鳥会長は、「まあ……茅野を助けようと思ってのこと……よね。仲間を助けようとしたあなたの気持ちは、評価してあげる。この湯呑の傷を見るたびに私はあなたのことを思い出すでしょうね」
感傷に浸る時間はないというように、湿っぽい空気を振り払い、飛鳥会長は立ちあがる。
「さ。ゑびちゃんにお礼でも言ってこようかしら。それじゃあね!」
飛鳥は生徒会室を飛び出していった。
思えばたくさんの善意によって、助けられた。茅野はすべてに感謝したい気持ちだった。
「本当に今日はありがとうございました」
あらためて彼女に礼をいう。
「困ったときは、お互い様です!」
にっこり答える彼女は、すこし深刻そうな表情になって、
「というわけで茅野さん。実はさっそく相談に乗ってもらいたいことがあって……」
なにかトラブルの予感を察知しつつ、茅野は「なんでしょう?」と問うた。
「実はですね……」
生徒会にトラブルは尽きない。茅野の頭を悩ます日々は、まだまだつづくのであった。
第4話・おわり