えりりは宿泊所の救護室で目覚めた。瞳に涙をうかべる彼女は、心底無念といった容子で、顔面蒼白だった。

「あら、おはよう。お目覚めね?」
白衣を着た小早川先生が声をかける。
「そろそろ自分の体力ぐらい、把握できるようにならないとねー」
なにも答えないえりりに代わって、荻原遥が「すみません」と謝る。
「どうせなら元気な時に遊びにいらっしゃいな」
「はい……」
「それじゃあ、もう大丈夫そうね」
「ありがとうございました」
えりりの肩を抱きながら、遥は宿泊所ホテルの自分たちの部屋に戻ってきた。
「今日はゆっくり休んで、富士山登頂はまた今度にしよう。ね?」
遥は精いっぱいの慰めの言葉を絞り出すようにして言った。えりりは「ほんとうにごめんなさい」とさらに肩を落とすだけだった。
「気にしない、気にしない!」どんよりした空気を追い払うように、遥は快活に言う。「みんなもう修学旅行の第二行程を楽しんでるんだから!」

「第二行程……?」
そこにわずかな希望を見いだすかのように、えりりが訊いてくる。
「そう! 富士急ハイランドとか、ロックフェスティバルもはじまってるんだからさ! 早く休養とって、いっしょに観覧車乗ろうよ」
「観覧車、ですか……」
「修学旅行は富士山のみにあらず! イベントが盛りだくさんなんだから、ぐずぐずしてられないよ」
「そうですね……」えりりはにっこり笑って布団にもぐりこんだ。「ありがとう、遥さん」
翌日、遥とえりりは富士急ハイランドへ向かった。フリーパスで入場ゲートをくぐりぬけると、メリーゴーランドや観覧車、ジェットコースターやお化け屋敷といったアトラクションが待ち受ける園内の景色が広がっていた。

「遊園地……実は10年ぶりくらいです」
えりりが遥の手を握りながら言った。
「そっか、ずっと病院にいたんだもんね……」
2人は廃墟の病院を模したお化け屋敷の前で足をとめた。
「どうする? お化け屋敷と観覧車、どっちがいい?」
「お化けは苦手ですぅ~」
その場で地団太を踏むえりりに対し、遥は「じゃあ、観覧車にしよ」と彼女の手を引いていった。
観覧車は5分間かけて一周する本格的なアトラクションで、高度があがれば園内と周辺の景色を一望できるのだった。
「うわあ~きれいですね!」
狭い観覧車のなかでえりりは体を揺らす。ハート型の窓枠が切り取る窓外の景色は格別だった。窓にぴったり両手をくっつけて、えりりは開放的な景色に見入っていた。
「富士山も見えます!」
えりりが遥に注意を促してくる。
「ねえ、せっかくだから、ここで記念撮影しよっか!?」
「はい、ぜひ~」
富士山と世界一のジェットコースターFUJIYAMAを背景に、遥とえりりは記念撮影をした。

宿泊所ホテルに戻って、ふたたびお土産コーナーを物色していると、えりりが「これはなんですかね?」と訊ねてきた。見れば『まくら』だった。

それは修学旅行名物〝枕投げ〟用のアイテムだった。紅白のチームに分かれて、ひたすら枕を投げるという枕大会が、ホテルで開催されているのだった。
「まくら、投げたいです!」
遥の説明を聞く間もなく、えりりは大きな枕を両手に抱えている。そんな彼女の姿を見て思わず噴き出した遥は、「よし! 参加しよっ」と同意した。

飛び交うまくらをうまく躱し躱しまくら投げをしていると、ひょっこりまくら以外のものが投げ込まれてくる。えりりのもとに飛んできたのは、『FUJIYAMA CHOCO IN COOKIES』だった。

「あれ? このパッケージ、お土産コーナーで買ったのとちょっとちがう……」
「あ!えりり危ない!」
結果、遥とえりりのチームは負けてしまった。だが枕大会のあと、仲良くなった友だちとロビーでしばらくおしゃべりをした。参加者たちと話し込んでいると、「それレアものの限定パッケージなんじゃない?」と言った。
「そうなんですか!?」
「よかったじゃん、えりり!」
「はい!」
それから遥とえりりは、まくら投げ大会で仲良くなった友だちとも合流して富士サファリパークに行ったり、ロックフェスティバルに行ったり。河口湖畔でボートに乗ったりした。
特に想い出深いのはやはり河口湖畔で、澄んだ湖面に逆さ富士が映り込んだ景色は絶景だった。遊覧ボートに乗った4人でかわるがわる記念撮影をしたものだった。

友だちと楽しい時間を共有する。時間やお金に制約された現実世界では、なかなか体験しえないすてきな時間を、遥とえりりは過ごすことができたのだった。
しかし、えりりにはまだ1つ、心残りがあった。
富士山登頂である。
「遥さん、もう一度チャレンジしてみたいんです……」
ご来光を拝む。交わした約束を果たしたい。そんな想いのこもったえりりに対し、遥は「わかった。行こう!」
「ありがとうございます!」
「ただし約束して?」
「はい……?」
「無理だけはしないって……」
えりりはひとつしっかりとうなずいた。
ご来光が見られるように早めに出発した遥とえりりは順調に登山行程をこなし、先日カレーライスを食べた新七合目山荘を通過し、九合目山荘にたどり着いた。大事をとって休むことにした二人は、おにぎりを頬張りながら、お土産コーナーで富士山ペアネックレスを見つけたのだった。
「遥さん、もしよかったら、記念に買ってみませんか?」
「え……」

なんだか恥ずかしい思いで言葉を濁した遥は、えりりの両目に見詰められ、ふっと笑った。
「そうだね。友情の証に」
「はい!」

まるでそれまでの疲れが吹き飛んだかのようだった。ペアの富士山ネックレスを身に着けた遥とえりりは、身体の内側から力が湧き出るように、ぐんぐんと最終工程へ――ひたすら山頂を目指していった。

間もなく『山頂富士館』と書かれた施設が眼前にあらわれた。えりりの肩をたたき、遥は「見て、えりり!」と看板を指さした。
「山頂……わたしたち、ついに登り切ったんですね!?」
「やった、着いたあああ!」

遥とえりりは抱き合い、飛び上がって登頂成功を祝した。また、富士山を登り切った記念にと、限定ペナントを手に入れた。
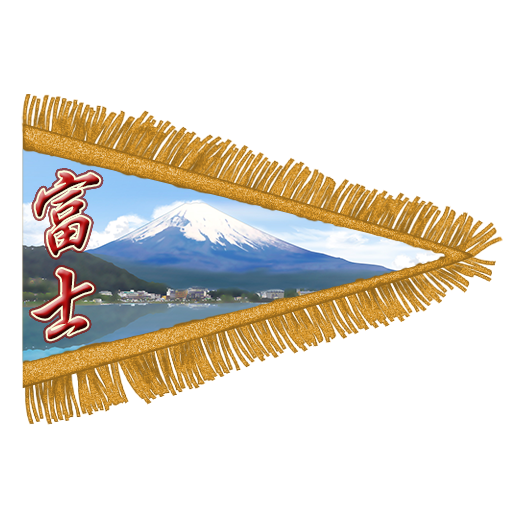
あとは、朝日が昇るのを待つのみだった。遥とえりりは、まだ明けきらない紺碧の空を眺めながら、おにぎりを頬ばっていた。
「遥さん……ほんとうにありがとうございました」
えりりはやさしくほほえみながら言った。
「どうしたの、急に改まっちゃって……」
「わたし一人では、絶対体験できないことばかり……ほんとうにたのしい修学旅行になったと思うんです」
「そうだね……」
いまから思えば、初めに登山に失敗したことも、あのときたべたカレーライスも、良き思い出になっている。そればかりではない。富士急ハイランドの観覧車から見た景色や、まくら投げ大会、あたらしい友だちと河口湖畔でボートに乗ったこと……。
思い返せば、ひとつひとつがかけがえのない思い出になって遥の胸にしまわれているのであった。
「こちらこそ、ありがとう」
遥も笑顔で応える。
「いままでで、最高の修学旅行だったよ……」
遥とえりりは、手をつないでご来光を待った。明るみはじめた紺色の夜空を注視していると、地平線の向こう側から、まばゆいばかりの陽がゆっくりと顔をだしはじめる。肌寒い空気に、ご来光の明かりがほんのりとぬくもりを与えはじめた。目を細めつつ、遥とえりりはなにも言葉をかわさずに、ただひたすらご来光を眺めたのだった。

おしまい

